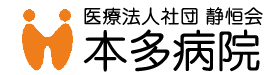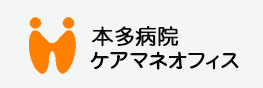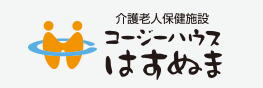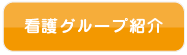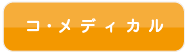![]()
![]()
![]()
80年ほど前に当院の前身である本多医院が現在地に開業以来、戦時中は怪我人の救護所となり、戦後結核が流行した時には結核患者を積極的に受け入れました。 現在は高齢化社会において、生活習慣病対策や糖尿病治療等に専門的な対応を行い、また腰痛、骨折などの整形外科的疾患や脳梗塞、脳出血などの脳血管障害に対するリハビリテーションを重視して治療を行っております。健康診断は大田区の健診も多く受け入れるなど、地域の皆様の健康を支えるお手伝いをさせていただいております。
今後も、コミュニティ&コミュニティホスピタル化によって、大田区蓮沼エリアの中核在宅療養支援拠点として、今まで以上に地域に密着し、地域に必要とされ、地域に貢献する、治し、支える医療の実現をめざして、職員一同力を合わせて頑張る所存でございますので、宜しくお願い致します。
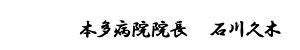
![]()
![]()
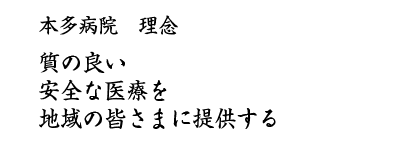
![]()
![]()
| 名称 | 医療法人社団静恒会 本多病院 |
| 所在 | 〒146-0094 東京都大田区東矢口1-17-15 |
| 電話番号 | 03-3732-2331(代) |
| FAX番号 | 03-3732-2335 |
| 設立 | 昭和10年 |
| 院長 | 医師 石川 輝 |
| 診療科目 | 総合診療科・内科・整形外科・リハビリテーション科・消化器内科・ 糖尿病内科・神経内科・呼吸器内科・循環器内科 |
| 病床数 | 47床 |
| 診療時間 | 月~金 9:00~12:00 15:00~17:45 土 9:00~13:00 日曜・祝日は休診。但し、急患は24時間受け付けます。 |
| 医療設備 | CTスキャナシステム X線透視撮影装置 内視鏡(胃・大腸) 超音波診断装置(心臓・胸腹部・その他) |
| 指定医療 | 東京都指定二次救急医療機関(休日・全夜間診療事業実施医療機関) 東京都脳卒中急性期医療機関 運動器リハビリテーション(I) 呼吸器リハビリテーション(I) 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ) 労災保険 生活保護 |
| 沿革 | 昭和10年:当院の前身である本多医院開設 戦後:26床の個人病院として認可される 平成2年:医療法人社団静恒会設立に伴い、24床の一般病院となる 平成12年:改築により47床の一般病院となる 平成19年:リハビリテーション室増築 平成26年:地域包括ケア病室設置 |
| 施設基準 |
■基本診療料 地域包括ケア病棟入院料1 救急医療管理加算 診療録管理体制加算3 後発医薬品使用体制加算2 病棟薬剤業務実施加算1 データ提出加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 医療DX推進体制整備加算6 一般病棟看護必要度評価加算(看護必要度Ⅰ) ■特掲診療料 夜間休日救急搬送医学管理料 及び注3に規定する救急搬送看護体制加算 ニコチン依存症管理料 薬剤管理指導料 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 CT撮影及びMRI撮影 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料39 ■入院時食事療養 入院時食事療養(Ⅰ)/食堂食事加算 |
入院基本料について
当院では、入院患者様10人に対して看護職員(看護師及び准看護師)1人、一日に11人以上の看護職員が配置されている体制で看護を実施しています。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
*8時30分から17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ちの入院患者様の人数は5人以内
*17時30分から8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ちの入院患者様の人数は12人以内
患者様負担による付き添い看護は実施しておりません。
また、寝具については、国の定める基準に合致したものを病院で用意しております。
入院時食事療養について
当病院の食事は、国の定める基準による「入院時食事療養(Ⅰ)」に適合しています。
食事を治療の一環と位置付け、管理栄養士がリーダーとなり、病状に応じた適切な給食を実施しています。
適時 (朝食: 午前8時、 昼食: 午後12時、 夕飯は18時以降)、適温で提供しています。
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当病院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
一般名処方加算・後発医薬品使用体制加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。
※「一般名処方」とは
医療用医薬品は「先発医薬品」と「後発医薬品」の二つに分類されます。「先発医薬品」とは、最初に発売された薬で、新薬とも呼ばれます。後発医薬品は、先発医薬品の再審査期間や特許期間(20~25年間)終了後に発売されるもので、ほぼ同じ成分、同じ効き目の薬で、ジェネリック医薬品とも呼ばれています。
医師が先発医薬品を指定して処方せんを発行するときは、「商品名」を記入しますが、特に新薬である必要がなく、後発医薬品が存在するときは薬の有効成分の名称である「一般名」を記入します。これを「一般名処方」と言います。国は、医薬品不足が続く現状のなかで、薬による治療が滞りなく行えるよう、「一般名」を処方せんに書くことで、保険薬局の在庫状況に応じて、先発品 後発品のいずれも調剤ができる状態にするため、「一般名処方」を推進しています。
※入院患者様の医療費抑制のため、「先発医薬品」の使用を推進しております。院内で調剤する薬について、万が一供給が不安定な場合、医師・薬剤師等が相互に協力して治療計画等の見直しを行う体制を作っております。医薬品の供給状況によって、使う薬を変更する場合は入院患者様へ十分に説明を行い実施します。
長期収載品の選定療養について
2024年の診療報酬改定10月から長期収載品の選定療養の制度が開始されました。この制度は、患者様のご希望を踏まえて長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様にご負担いただくものです。ただし、医師が、医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。ご不明な点はご相談ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年以上が経過しているものや後発品置換え率が50%以上のものなどの要件に該当する医薬品です。対象医薬品は、厚生労働省のホームページで公表されています。
※選定療養とは、保険診療と保険外診療を併用できる制度のひとつであり、保険外診療にあたるものです。保険給付ではないため、消費税が別途かかります。
長期処方・リフィル処方せんについて
当院では生活習慣病など慢性疾患の患者様が増えていることに対応し、症状が安定している患者様に対して、お薬の『28日以上の長期の処方を行うこと』・『リフィル処方せんを発行すること』のいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します
※生活習慣病(糖尿病)の患者様には、気になる症状がなくても歯科(歯周病)・眼科(糖尿病網膜症)の受診をおすすめしております。ご希望の方は、担当医へご相談下さい。
医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について
当院では「マイナ保険証」をご利用いただけます。マイナンバーカードによる保険証の確認およびオンライン資格確認を行う体制を有しています。受診した際に、マイナンバーカードによる保険証の確認とともに薬剤情報や特定健診情報、その他必要な情報の取得に同意いただいた方に対して、その情報を活用し診療を行います。医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう、「マイナ保険証」を利用した保険資格の確認をお勧めしております。
※マイナ保険証を利用した場合の利点
患者様に同意をいただいた場合、他の病院・診療所、調剤薬局等での「お薬の履歴」「診療の情報」「特定健診の情報」を、当院の医師、薬剤師等の有資格者が閲覧し、診察に役立て、医療の質の向上に努めます。
入院・手術等でお支払いになる医療費が高額になるとき、「限度額適用認定証」がなくても、手続きなしで、限度額以上の支払いが不要になります。
特別療養環境の提供について
当院は特別療養環境室(個室等)の設置が認められている保険医療機関で、患者様のご希望と同意に基づいて利用することが出来ます。特別療養環境室(個室等) の料金は以下の通りです。
下記の部屋については、一日につき以下の金額を室料差額として患者様にご負担頂くこととなっていますので、あらかじめご了承下さい。

なお、「施設管理費」や「お世話料」などの名目での費用徴収は、一切行っておりません。
禁煙外来について
当院は、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもなかなかやめられない等のお悩みの方等に対し、禁煙のお手伝いが出来るように禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行っています。ご希望の方は主治医又は外来看護師・受付までお申し出ください。
※診療内容
<喫煙状況とニコチン依存度の調査、呼気中一酸化炭素濃度測定、禁煙アドバイス、治療薬使用等>
※病院内とその周辺は全面禁煙ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします
診療録開示に伴う費用について
*開示請求手数料¥2,200(税込)
*診療録(書面)の複写1枚¥55(税込)/ カラー複写1枚¥110(税込)
*レントゲン・CTの画像等複写(CDにて提供)¥1,100(税込)以上
診療情報等の提供・開示に関しては、取扱規則に定める手順で行います
※申し込み方法 所定の診療情報開示請求書に必要事項を記入していただきます。用紙は相談窓口にてお渡しいたします。(原則として、電話等での開示請求はお受けできません。)
※ご注意いただきたいこと
対象となる診療情報の開示が、患者さま本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合や、第三者の利益を害する恐れがある場合は、申請に応じられないことがございます。
※診療情報の開示について不明な点などがある場合は、1F医事課受付窓口までお問い合わせください。
在宅医療情報連携加算
患者様の診療情報などについて、5つ以上の連携医療機関とICTを用いて共有し、常に確認できる体制を有しています。
診療情報などの共有に同意された患者様について、連携医療機関以外の保険医療機関などと、ICTを用いた情報を共有する連携体制を構築しています。
厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応しています。
【連携先一覧】※五十音順
あいず訪問看護ステーション練馬
アエルバ訪問看護ステーション
おうちのカンゴ上池台支所
ケアズファクトリー蒲田
ケアプランさくら
ケアプランそ・ば・に
キュエル訪問看護ステーション
ソフィアメディ訪問看護ステーション大鳥居
ソフィアメディ訪問看護ステーション大森町
チームハル
仁済ケアプランセンター蒲田
仁済訪問看護ステーション
大田ケア訪問看護ステーション
薬樹薬局はすぬま
メディアス訪問看護ステーション
訪問看護ステーションリカバリー
![]()
![]()
当院では、次の事項については患者様にご負担いただくことになっております。

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」 についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
2024年11月
![]()
![]()
私たち看護職員は看護部理念である「心のこもった看護」を目指し日々努力しています。病気になると体だけではなく、心も弱ってしまうものです。患者さんが一日も早く心身共に回復されるよう、安心して治療が受けられるようお手伝いさせていただきます。
当院の看護グループで働く看護職員は常勤・非常勤合わせて約30名おります。20代から50代まで幅広い年齢層の看護職員がおり、様々な意見交換を行いながら看護の向上に努めています。
また、看護グループだけではなく、医師・薬剤師・リハビリスタッフ・ケースワーカーなど他部門との連携も大切にしています。病棟カンファレンス、勉強会なども定期的に行い、小規模な病院だからこそできる医療の充実を目指しています。
![]()
![]()
| 薬事グループ | お薬を安全に使用するために、日々変化する情報を管理し、正しくお薬を服用して頂くために、薬剤師が患者さんの病室に伺い、服薬の指導を行っております。 |
|---|---|
| 放射線グループ | X線一般・透視撮影検査、CT検査などを行っています。検査による放射線被ばくに関しても相談に応じています。 |
| ケース・カンファレンス | 医師・看護師・薬剤師・リハビリスタッフ・管理栄養士・医療相談員などにより、入院されている患者さん1人ひとりの診療方針の検討会を行っています。 |
| 医療相談室 | 病気になると、健康なときには思いもよらなかった心配事が生じる場合があります。患者さん・ご家族・主介護者などの方々と、入院中の心配事や退院に向けた準備などを、より良い生活環境にするためにともに考えていくお手伝いをいたします。 |
| 栄養グループ | 入院患者さんの疾病治療、健康回復のため、病状にあわせた治療食を提供しています。 食事には、常食・粥食・流動食など5種類の一般治療食と熱量コントロール食・蛋白コントロール食・脂質コントロール食など16種類の特別治療食があります。 四季折々の行事食を毎月実施し、手作りのメッセージカードが添えられます。 管理栄養士が 安全で美味しい治療食づくりをめざしています。 治療食への理解を深めていただくために、糖尿病、高血圧症、腎臓病などの栄養指導を個別に行っています。また、退院後自宅での食事についてご家族も含めて指導相談を行っています。 また、少人数制の食事教室を栄養相談室にて開催しています。この教室は、入院に限らず、外来の患者さんも参加することができますので皆様の参加をお待ち申し上げております。 管理栄養士は、入院患者さんの栄養状態を把握し、それぞれの患者さんにあった栄養管理計画を作成し、病棟のスタッフとともに、患者さんの栄養状態の改善、病態及び療養生活の質の向上を図るよう努めております。 |
行事食の一例

お正月

七夕

クリスマス

嚥下調整食
| リハビリテーション科の 理念 |
安心安全で質の高いリハビリテーション医療を提供するとともに、これから始まる新しい生活に向けて患者さんの生きがい・尊厳を重視した医療を提供します。 |
|---|---|
| 対象疾患 | 脳梗塞・脳出血・パーキンソン病等の脳血管疾患 骨折・変性疾患・術前術後の整形外科疾患 慢性閉塞性呼吸不全・肺炎等の呼吸器疾患 神経筋疾患・呼吸器疾患・心疾患・長期臥床による廃用症候群 |
| 介入頻度 | 入院 週5~6日 20・40分~(祝日も対応している場合あり。) ※患者さんの状況に合わせて、頻度・実施時間を変更しています。 外来 週2~3回 相談の上決定 |
当院は、それぞれの時期(急性期~亜急性期、在宅)に応じた早期在宅復帰を目指したリハビリテーションを行っております。病気や外傷によって身体的・精神的な障害が起こってしまった方に対し、できるだけ日常生活に早く戻れるように入院・外来にて介入しております。
作業療法では、患者さんの日常生活に関わる全ての活動である「作業」に注目し、早期自立・早期退院を目指し、病期に合ったリハビリを行います。
食事・着替え・トイレ動作などの日常生活活動練習や、アクティビティーを取り入れた認知機能訓練、在宅復帰を目指す患者さんには、キッチンや浴室での動作練習なども行います。
病院の様子

![]()